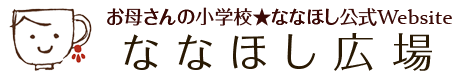| 子どもが4歳くらいになると体験学習に参加する機会もでてきますよね。色々な体験をして欲しいのに子どもが嫌がって行かないという悩みも…。我が家が実践したおすすめの方法でチャレンジを嫌がるお子さんに新しい体験のチャンスを作ってあげましょう! |
体験学習ってどんな目的?
みなさんのお子さんは「体験学習」に行かれたことありますか?
身近なところだと遠足や〇〇狩り、おいもほりなど園の行事だったり職業体験施設なども人気がありますよね。
体験学習は、生きる力の基盤をつくるために必要なことと言われています。
・テレビやゲームばかりではなく、現実世界に興味・関心をもち、生活する意欲をアップさせる
・自分で考えて理解する力がつき、問題があったら解決する能力を身につける
・自分を認める感情を成長させる
・お友達と協力するなど、自分以外の人と共に生きることを学ぶ
など、幼児期の子どもにもたくさん経験してもらいたいことばかり!
私も息子が4歳の年中になり、そろそろ体験学習を色々経験させてあげたいな、と思っていたのですが、我が家の息子は初めてのコト、場所が苦手です。
幼稚園ではお友達や先生にも慣れてきて、園の行事の体験学習は楽しく参加できるようになってきましたが、習い事の体験や、大好きなストライダーの大会など息子が興味ありそうだな!と思って誘ってみても「いや、行かない!」と決まり文句のように言います。
私はもう少しチャレンジする力をつけて「やってみたら楽しかった!」という経験を増やしてあげたいなと思っていました。
そんなとき、幼稚園の夏休みに入りお友達から「ピザ屋さんの体験学習があるから行ってみない?」とお誘いを受けました。
いつもの私なら息子にやるかどうかを聞いてから返事をするのですが、慣れているお友達も一緒で、場所も家の近く、母子分離を経験でき、ママはカウンター越しに見ていられるという好条件が揃っています。
今回はまたとないチャンス!と思い、私の一存で参加することを決めました。
「さて、どうやって息子を誘おうかな…」
体験日まで2週間。息子に「行く!」と言ってもらえるよう、私の作戦スタートです!

なぜチャレンジすることが苦手なの?
作戦をご紹介する前に、なぜ息子が新しいことのチャレンジが苦手なのか、息子の特性も合わせてお話したいと思います。
息子は少し衝動性があり、不安になりやすいところがあります。
コミュニケーションを学ぶ前の3歳頃までは、癇癪も激しくいつでもどこでもママべったりで「ママと一緒がいい」が口癖のような感じでした。
公園でやったことのない遊具にチャレンジをすることもすごく嫌がりましたし、やるとしても私がつきっきりでサポートしていないとだめでした。
息子が体験を嫌がる主な理由は「怖い」と「ママと一緒ならいい」の2つでした。
ではその理由を掘り下げてみましょう。
◆怖い
息子の言う怖いは「高い、速い」などの物理的なことよりも「それがどんなものなのかがわからなくて怖い」という漠然とした不安からくるものが多いです。
不安をつくりだすのは、脳の感情系エリアが関わっていて自分の気持ちを感じたり、作り出したりしています。
例えばやったことのない公園のブランコを「やってみない?」と言われたとき、子どもは視覚や聴覚からブランコの動きやお友達の表情、楽しそうな声を感じ取ります。
その感じ取った情報が、自分にとってポジティブかネガティブかなどを判断するのが「自分の気持ちを感じること」です。
そしてその情報から楽しそうだから「やってみたい!」や怖そうだから「不安」と思うことが、感情を作り出すということになります。
初めての体験学習のように、まだ過去に経験がないことをするというのは、子どもにとっては実際見たことも聞いたこともないこと。
判断する情報がないため、見通しが立たずいったいどうすればいいのか分からないという状態になり、不安な気持ちでいっぱいになってしまいます。
ですから、子どもに初めての体験学習の説明をするときは、できるだけ本人が想像しやすいものにすることが大切になってきます。
◆ママと一緒ならいい
息子の口癖といってもいいのが「ママと一緒ならいい」です(笑)
今はだいぶ言わなくなりましたが、初めての体験や母子分離のとき(男子トイレにパパと行く)などのときも、息子の状態によっては今も言います。
なぜママと一緒ならいいと言うのでしょうか?
それは脳が不安な気持ちを対処するために選択する、1つの方法なんです。
やってみたいけど怖いという状態のとき、1人では無理そうだけど、ママという安心できるものがあればできそう!と思っているのです。
脳の仕組みでも、苦手な刺激は快刺激(自分が好きなもの)と一緒に行うと、克服しやすいということが分かっています。
子どもの脳も本能的に大好きなママを快刺激として利用しているんですね。
私はそれを知らなかったときは「甘えていないで自分でやってみなよー」と思っていましたが、苦手な刺激+快刺激のことを理解してからは、「嫌だと思っているけど、乗り越えようとしているんだな。サポートしよう!」と前向きにとらえるようになりました。
このように、自分の子どもを分析して原因を探ってみると、やみくもに対応するよりもより具体的な方法が浮かんできます。

では私が立てた作戦をご紹介しますね!
あわせて読みたい!▼
チャレンジを助ける3つの方法
今回、ピザの体験学習を誘ったときの息子は興味はもってくれたのですが、ピザ屋さんに行って作る、ママは一緒に作らないと分かると「それは行かない」という返事でした。
私の中では想定の範囲(笑)でしたので、次の3つの作戦を決行しました。
◆写真や動画で状況説明
子どもに説明をするときついつい言葉だけで伝えてしまいがちですが、幼児期の子どもは言葉だけで状況を想像するのはとても難しいです。
そんなときは、幼児期の子どもの脳が得意な写真や動画などで、目で見てすぐにわかる方法で伝えましょう。
今回の体験をした「ドミノピザアカデミー」とネット検索すると、体験の様子の写真がたくさん出てきました。
「ちょっとこれ見てー!〇〇くんくらいのお友達がたくさん写ってるー!楽しそう~」
と写真を見るよう誘いました。
スマホで写真を見るのが好きな息子はすぐに駆け寄り写真を見て
「ほんとだ!なんかエプロンしてるね」と笑顔。
「そうそう、エプロンと帽子もかぶってやるんだって!かっこいいね!」と伝えましたが「でも行かない」との返事が(笑)
これも想定の範囲です!
(この段階で行く!と言ってくれるお子さんもいると思います^^)
簡単に行くと言わない息子ですので、次の作戦を決行します!
◆家で疑似体験
息子のように安心できる場所や人と一緒ならやってみたい!と思っているようでしたら、家での疑似体験もおすすめです。
実際に体験する場所で何をするのかの見通しが立っていないことの不安もありますから「こんなことやるんだよ」という体験の真似を事前にしてあげると、子どもは安心できます。
いわゆる、予習ですね!
私は「ママがお家で作ってるピザトーストあるでしょう?あれと似てるから、一緒にやってみる?」と誘いました。
すると息子は「やるやるー!」と満面の笑み。
具材を小皿に1つずつのせて並べ、手でつかんでパンにのせやすいように体験の再現をします。
手元に見本用のママの食パンと、隣に子ども用の食パンを置き「まずはケチャップをこうやってぬりまーす」とゆっくり教えていきます。
そして作業しながら「ピザ屋さんでもこんな感じでやるみたいよー。〇〇くん、できてるね!」と、ピザ作りの心配はもうなさそうだよ!ということを伝えます。
楽しく予習することがポイントですから、子どもの作るものは手出し、口出しはせずに「そうそう!のせられたね!おいしそうになってきたじゃん!」など、ポジティブな声かけをしてくださいね。
◆できるかどうかは別として!
ここまでできたら、次は実際行くかどうかの回答をもらうための作戦です!
息子のように少し心配性なところがある子どもにおすすめの声かけの言葉があります。
それは「できるかどうかは別として」という言葉です。
「できるかどうかは別として」と最初につけると、チャレンジすることへのハードルが少し下がる印象になります。
チャレンジすること自体「できるかどうかは別として」という意味や、チャレンジすることの結果に対して「できるかどうかは別として」という意味など、お子さんの状態に合わせて使うといいですね。
私も作ったピザを食べながら「できるかどうかは別として、ピザ体験行ってみない?」と話してみました。
すると「教えてくれる人はやさしい?男の人?女の人?」と少し前向きな発言が出てきました。
私はすかさずサイトの写真を見せて「こんな感じの人だよー!見て!すごい優しそうだよー!!」と伝えると「うん。そうだね。男の先生なの?」と質問が。
「男の人か、女の人かはまだ分からないんだけど、教えてくれる人はみんな優しい人だよ!」
「行ってみる?」
と伝えると「行ってみる」と言ってくれました!
「ママ、〇〇くんが行ってみるって言ってくれて、とっても嬉しい!!」と息子の決断をしっかり褒めて、体験に誘う作戦が無事終了しました。
そうして当日も終始お友達と「あーでもない、こーでもない」と話をしながら楽しくピザを作ることができ、息子にとって「やってみたら楽しかった!」という成功体験をさせてあげることができました。

息子のように不安があったり、母子分離が苦手というお子さんのママは、チャレンジさせたいと思っても難しいことがあると思います。
ですが、お子さんの特性を理解して、お子さんにあった方法を見つけていけば、必ず成功体験をさせてあげることができます。
ぜひ、ママ自身も「この方法でやってみたら楽しくうながせた!」という成功体験を増やして、楽しい育児を一緒にしていきましょう^^
今日もお子さんとの楽しい時間がすごせますように。
執筆者:宮代さちこ
あわせて読みたい!▼
▼子どもの特性を知ってママもラクに育児する!そんな扉を開く第一歩は簡単登録のメルマガから。新しい世界がまっていますよ^^